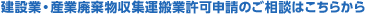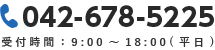産業廃棄物収集運搬業とは?~許可取得のポイントと注意点~
環境問題への関心が高まる中、「産業廃棄物収集運搬業」は社会インフラの一端を担う重要な業種です。企業が製造・建設活動を行う際には、必ずといってよいほど廃棄物が発生します。その中でも、一般家庭ではなく事業活動から生じた廃棄物は「産業廃棄物」とされ、専門の業者によって適切に運搬・処分されなければなりません。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業を始めるために必要な許可、申請時の注意点、実務で気を付けるべきポイントをわかりやすく解説します。
1. 産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、事業所などから発生する産業廃棄物を、排出現場から中間処理場や最終処分場まで運ぶ業務です。これを業として行うには、**廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業の許可」**が必要です。
この許可は、運搬のみを行うもの(「収集運搬業」)と、処分まで行うもの(「処分業」)に分かれています。運搬業の場合でも、扱う廃棄物の種類によって許可内容が細かく分かれており、許可を取得していない種類の廃棄物を運ぶことはできません。
2. 許可取得の流れと要件
2-1. 許可申請の基本
許可を取得するには、各都道府県または政令市に申請を行う必要があります。つまり、収集運搬を行う地域ごとに許可が必要です(例:東京都→東京都の許可、大阪府→大阪府の許可)。
申請時には以下のような書類が求められます:
-
申請書(所定様式)
-
定款、登記事項証明書
-
財務諸表
-
使用する車両・容器の一覧
-
講習修了証(責任者のもの)
-
事業計画書 など
2-2. 主な要件
許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 講習会の受講
申請者または事業所の責任者は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する「産業廃棄物収集運搬業講習会」を受講・修了している必要があります。
(2) 欠格事由に該当しないこと
過去に廃棄物処理法違反があった、暴力団との関係がある等の場合、許可を取得できません。
(3) 財務的基盤があること
赤字決算が続いている法人や債務超過の場合、経営の安定性が問われ、許可が下りにくくなります。
3. 実務上の注意点
3-1. 「許可の範囲」を正確に理解する
許可には「扱える産業廃棄物の種類」が明記されており、それ以外の廃棄物を運搬することは違法行為となります。例えば「金属くず」はOKでも、「廃油」はNGというケースがあり得ます。契約を結ぶ際には、廃棄物の内容と自社の許可内容が一致しているかを必ず確認しましょう。
3-2. 委託契約書とマニフェスト管理
収集運搬を行うには、排出事業者との間で委託契約書を締結し、**マニフェスト(産業廃棄物管理票)**を適切に運用する必要があります。マニフェストとは、廃棄物の流れを記録・管理するためのもので、不適切な処理を防止するために非常に重要なツールです。
マニフェストには紙媒体(紙マニフェスト)と電子媒体(電子マニフェスト)があり、近年は後者が主流になりつつあります。

4. 許可の更新と変更手続き
産業廃棄物収集運搬業の許可は5年間の有効期限があり、期限が切れる前に更新申請を行わなければなりません。また、以下のような変更があった場合は、変更届または変更許可申請が必要です。
-
使用車両の変更
-
会社の代表者の変更
-
本店所在地の移転
-
会社の名称変更 など
これらの届出を怠ると、許可の取消しや更新不可のリスクもあるため、日々の運営管理にも注意が必要です。
5. 行政書士のサポートが有効な理由
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、必要書類が多く、書類作成や役所とのやり取りに時間がかかる場合があります。また、書類不備による差し戻しも少なくありません。
そのため、伊橋行政書士に依頼することで以下のようなメリットが得られます:
-
確実・スムーズな申請手続き
-
忙しい事業者の業務負担を軽減
-
実務での注意点や今後の展望に関するアドバイス
とくに新規参入を検討されている方にとっては、最初の一歩を安心して踏み出せるサポート体制があることは大きな安心材料となります。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業は、環境保全に貢献するやりがいのある事業ですが、法的なルールに基づいて運営することが求められます。許可取得には、準備すべき書類や満たすべき要件が多くありますが、正しく理解し、必要な手続きを進めていけば決して難しいものではありません。
もし、許可取得や更新手続きに不安を感じている方は、ぜひ一度、伊橋行政書士法務事務所にご相談ください。専門家のサポートを受けながら、安心して事業のスタートを切りましょう。