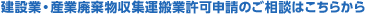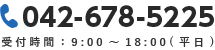行政書士が教える!産廃収集運搬業許可の取得から事業成功までのステップ
はじめに:許可取得は“稼ぐ仕組み”を作る第一歩
「産業廃棄物収集運搬業」は、建設業・解体業などと並び、今後も安定した需要が見込まれる事業分野です。しかし、許可を取っただけで安定的に利益を生み出せるわけではありません。
実際に稼いでいる業者は、単なる運搬だけではなく、複数の“キャッシュポイント”を事業に組み込む工夫をしています。
本記事では、行政書士の立場から「許可取得後、実際に収益化している産廃業者の特徴」や「利益を出すための構造」について、分かりやすく解説します。
ステップ1:まずは「単価が取れる廃棄物」を狙え
高単価な廃棄物を扱うことで利益率アップ
産業廃棄物にはさまざまな種類がありますが、運搬単価が高くなりやすいのは以下のようなケースです:
-
建築系混合廃棄物(解体現場などから出るもの)
-
石綿含有廃棄物(特殊処理が必要なため高単価)
-
医療系・機密書類等の特別管理廃棄物(運搬管理が厳格)
これらは一般的ながれきや金属くずと比べて処理費・運搬費が高く、利益を出しやすい案件です。
「単価の安い廃棄物ばかり扱って消耗する」のではなく、「運ぶ内容で利益率を高める」ことが第一のキャッシュポイントです。
ステップ2:ルート契約・定期契約で安定収益を確保
単発対応ではなく「定期回収」がカギ
安定的に収益を上げている業者の多くが重視しているのが、ルート契約の獲得です。たとえば:
-
建設会社・リフォーム会社との月額契約
-
テナントビルや商業施設の定期回収契約
-
地元自治体との委託契約(入札参加)
単発案件は確かに単価が高いこともありますが、案件がなくなるリスクや待機コストが発生します。それに比べて、月ごとの契約があれば、一定の売上が見込め、資金繰りの見通しも立てやすくなります。
ステップ3:「積替保管許可」で運搬エリアと利益を拡張
中継拠点が“収益の幅”を広げる
通常の収集運搬業許可では、「排出場所から処分場まで直行」しなければなりません。しかし、「積替保管」の許可があれば、自社のヤードなどに一時保管ができ、以下のようなメリットが生まれます:
-
長距離の廃棄物も一括してまとめられる → 輸送コスト削減
-
処分業者のスケジュールに合わせて調整 → 待機時間削減
-
他業者の廃棄物もまとめて運搬 → 共同運搬で追加収益
この積替保管を上手く使うことで、“広域対応+効率化”による利益の最大化が可能になります。
ただし、積替保管許可は土地の確保、地域住民への説明会やコンセンサスなど要件が何倍も上がります。反面、事業規模を拡大したい業者にとっては大きなキャッシュポイントになります。
ステップ4:資源リサイクルで「運ぶだけ」からの脱却
廃棄物から価値を生む仕組み
近年、「廃棄物=コスト」から「廃棄物=資源」への転換が進んでいます。これをビジネスとして活かすには、以下のような工夫が有効です:
-
金属・プラスチック等の分別回収 → 売却
-
解体廃材を自社で選別・再資源化
-
再生材を建材業者へ販売
単なる運搬から一歩進んで、「処分前の選別」「資源化」まで手を広げることで、処分費の削減+リサイクル収益の獲得ができます。
たとえば、鉄くずを一定量以上ストックして業者に売却するだけでも、月数十万円規模の副収入になるケースもあります。

ステップ5:他事業とのシナジーを生む仕組み
産廃業だけにこだわらない視点も重要
成功している収集運搬業者は、以下のような「関連業務との組み合わせ」で収益を多角化しています:
-
解体業を併設して、現場→運搬までワンストップ対応
-
不用品回収・遺品整理と組み合わせて高単価化
-
設備・土木業者とのグループ化で仕事の回し合い
これらは単に運搬するだけでなく、顧客の「片付け」や「廃棄ニーズ」をトータルで請け負うことで、単価アップと案件増加を狙える戦略です。
まとめ:産廃業で“稼げる”業者は何をしているのか?
産業廃棄物収集運搬業は、単なる許可ビジネスではなく、工夫次第で収益性の高い事業になります。
許可取得後の事業成功のために必要なキャッシュポイントをおさらいすると:
-
高単価廃棄物を扱う選別眼
-
定期契約・ルート案件での安定化
-
積替保管許可による広域・効率化
-
リサイクル収益の獲得
-
他業種との連携によるシナジー創出
これらを意識しながら事業設計を行えば、競争が激しい中でも確実に利益を出せるモデルを築くことができます。
産廃業で許可を取得したけれど「これからどうやって稼ぐか分からない」という方へ。
伊橋行政書士法務事務所として、許可取得後の戦略や各種法令の運用まで、トータルで支援可能です。
ぜひ一度、ご相談ください。