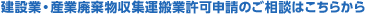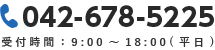【裏話】行政書士が語る!運送業許可の現場あるある~荷主と運行管理者とのリアルなやりとり~
こんにちは、八王子市の伊橋行政書士です。
今日は少し趣向を変えて、「運送業許可申請の裏話」…つまり、行政書士として関わる“現場”でのあるあるエピソードをご紹介したいと思います。
運送業許可と聞くと、なんだかお堅い書類仕事のイメージがありますが、実は現場は予想外の出来事の連続。行政書士の仕事は、単に書類を整えるだけでは終わらないのです。
◆書類より大変!?荷主との絶妙な距離感
ある日、運送業許可のご依頼をいただいた中小運送会社の社長さん。すでに荷主との取引が始まっており、「急いで許可を取りたい」とのご相談でした。
「許可が下りるのに2か月くらいかかりますよ」と伝えると…
「それだと荷主に怒られるんですけど…どうにかなりませんか?」
と、少し困った顔。荷主側は「許可はすぐに取れるもの」と思っていたようで、話がすでに進みすぎていたのです。
こうしたケース、実はかなり多いです。
運送業界では「まず仕事ありき」で動くことが多く、法令よりも実務が先に走ってしまうことがしばしば。伊橋行政書士としては、「それはダメです」と一刀両断するわけにもいかず、クッション役として荷主との調整まで請け負う羽目になることも。
結局このときは、社長と一緒に荷主さんへの説明用資料を作成し、スケジュールを理解してもらうところから始めました。
◆「運行管理者はうちの経理の〇〇です」←本当に大丈夫?
次によくあるのが、運行管理者の選定に関するあるあるです。
申請には「選任予定の運行管理者」が必要ですが、「うちの事務員が持ってるから、それでお願いします」というケースも少なくありません。
ある会社では、提出前のヒアリングで「運行管理者は経理担当の〇〇さん」と伺ったので、念のためお話を聞いてみると…
「え?講習は受けましたけど、現場のことは何も分かりません。車両も見たことないです。」
という返答。
つまり**運行管理者の“名義貸し状態”**だったのです。
これでは申請しても、現地確認などで“実態が伴っていない”と判断され、下手すると不許可になる可能性もあります。
急遽、実際に運行管理に関わっている社員の方に講習を受けてもらい、なんとか間に合わせることができました。
行政書士としては、「名前さえあればいい」ではなく、実態を伴った管理体制が必要だということを、丁寧に伝える必要があります。
◆「営業所」と「車庫」は、実は“家族の土地”…よくあるパターン
運送業許可では、営業所や車庫の使用権限も重要なポイント。
ところが、いざ申請書を作ろうとすると、「土地の名義が親族になっている」ことが判明することも。
たとえば…
「ここはうちの土地だから使っていいんです!」
と言われても、登記簿を見るとお父さんの名義。しかも、そのお父さんが遠方に住んでいて、印鑑証明の取得が難しい…という流れ。
このパターン、想像以上に多いです。
本人は「家族だから問題ない」と思っていても、申請上はきちんと賃貸借契約書や使用承諾書が必要です。伊橋行政書士としては、その説明から関係者への調整、必要書類の取得までをやらなければならず、書類作成の数倍時間がかかることもあります。
◆「人がいない!でも許可取りたい!」というジレンマ
人手不足が深刻な業界だけに、「運転手が1人しかいないんだけど、許可取れますか?」という問い合わせも珍しくありません。
原則としては常勤運転者2名以上が要件。
でも現実には「1人+アルバイト」や「社長が1人で運転してる」というケースも多く、どうにか工夫しながら要件を満たす必要があります。

ある案件では、社長が親族を一時的に従業員として雇用することで、要件を満たしました。その際の就業実態や給与支払いについても丁寧に記録し、「見せかけでない」ことをアピールする資料も添付。
ここでも、法令と現場のリアルの狭間で、行政書士の調整力が問われます。
◆現場に入ってこそ見える「本当の信頼関係」
こうしたエピソードを通して感じるのは、行政書士が単なる“書類屋”ではなく、クライアントのビジネスパートナーとして信頼される存在になっていくことの大切さです。
申請書を出すまでのプロセスには、大小さまざまな壁があります。でも、それを1つずつ一緒に乗り越えることで、単なる「代書屋」ではない、信頼関係が築かれていきます。
実際、「次は産業廃棄物の許可もお願いしたい」「社員の就業規則も見てくれないか」と、仕事が広がっていくのもこの分野の面白さです。
◆まとめ:運送業許可は“現場と人”が命!
運送業許可は、単に「法令に沿って書類を整える」だけでは通用しません。
実態の把握、関係者との調整、現場の事情への理解が欠かせず、むしろそこに行政書士の“価値”があるとも言えます。
「机上の知識」では対応できない現実の中で、伊橋行政書士法務事務所としてどんなふうに動くか。
それが、他の専門職との差別化にもなり、リピートや紹介につながっていくのだと感じます。